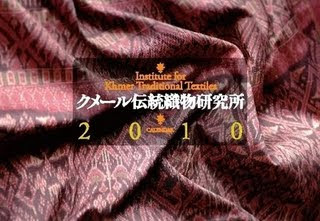わずか数日の日本での滞在だったが、ちょうど千駄ヶ谷で開催されていた「うちくい展」という催しを見に行くことができた。会場は、新宿御苑のすぐ隣、というか新宿御苑の森を借景にした「ラミュゼdeケヤキ」という名前の素敵なお家。この「うちくい展」、おもに沖縄で手作りの布に取り組まれている方々の作品展。風合いのある、素敵な布たちに出会えた気がする。
そして、そんな布を見て、少しほっとした。というのは、昨年の11月、沖縄の南風原文化センターの「アジア・沖縄 織りの手技」展に招かれたとき、琉球絣の産地で出会った布たちの表情には、少し元気がなかった。なぜかといえば、素材の糸がもつ無表情な印象が気になったのだ。それは多分、中国あたりで機械引きされた無機質な生糸のせいなのだと思う。絣の仕事や織りそのものには手がかけられているだけに、それはとても残念な出来事。沖縄の織り手たちが、その素材としての生糸をもう一度見直す時期に来ているのだと、改めて感じた。でなければ、せっかくの手仕事が浮かばれない。
素材、それはそのまま風土という言葉に置き換えられる。風と土、それは自然環境そのものである。その土地の生態系を生かした産物、それが素材といえる。しかし、現代の効率化と大量生産の時代のなかで、素材はマーケットから買うのが当たり前になってしまった。でもそれは、誰がどんな風に作っているのかが見えてこない、固有の風土とは無縁なもの。アンデスの山の中で、昔ながらの腰機(こしばた)で織られている布も、その糸はマーケットから買った化学染料で染められた化繊の糸になってしまっている時代である。それは、安全性も含めて、作り手が見えなくなってしまった輸入食料品の世界にも似ている。結果として、それが生み出されている風土とは無縁なものづくりが、当たり前になってしまった。
「うちくい展」の布を見て、触って、そんなことを考えていたとき、会場に今井俊博さんが現れた。偶然のこととはいえ、本当にびっくりした。今井さんは、目白で「ゆうど」という自然素材にこだわった布などを扱うお店を主宰されている。じつは、わたしが彼から素材の大切さに眼を向けるきっかけをいただいたのは、14年ほど前に、今井さんとお会いしてお話をお聞きしたときだったように思う。もう80歳を超えられているのではないだろうか、でも杖をつきながら、でもお元気な姿を、久しぶりに拝見した。今井さん、展示されている布の前に腰を下ろして一言、「沖縄でも、本当に素材からこだわっている作家が少なくなったんだよね」。
その今井さん、70年代のファッショナブルな時代の最先端だった広告業界の中で大きな仕事をされてきた方だと聞いている。
 そして80年代には、インドネシアで手で布を作る人々との出会いがあったという。96年に国際交流基金主催の『アジアのテキスタイル交流プログラム』を企画され、そのときにお会いしたのが最初だった。ラオスやタイ、インドネシアやインドなどアジア各地の布にかかわる人たちと出会い、互いに刺激を受けながら、東京、京都、沖縄と日本の布にかかわる人たちとも交流することができたプログラム。それは、わたしにとっては、ちょうどIKTTをカンボジアで設立した直後のことでもあった。
そして80年代には、インドネシアで手で布を作る人々との出会いがあったという。96年に国際交流基金主催の『アジアのテキスタイル交流プログラム』を企画され、そのときにお会いしたのが最初だった。ラオスやタイ、インドネシアやインドなどアジア各地の布にかかわる人たちと出会い、互いに刺激を受けながら、東京、京都、沖縄と日本の布にかかわる人たちとも交流することができたプログラム。それは、わたしにとっては、ちょうどIKTTをカンボジアで設立した直後のことでもあった。西表島の紅露工房を主宰されている石垣昭子さんと金星さんにお会いしたのもそのときだ。お二人の染め織りの素材との自然なかかわり方から、多くのことを学ばせていただいた。わたしにとって大切な出会いのときだった。西表の谷合の沢に自生する琉球藍の葉を収穫しながら、そのいくつかを次のために植え直してゆく。紅露(くーる)という芋の仲間を山から収穫するときも、収穫するのは半分だけ。残りは、土の中に残してやる。それは、風土を愛し、循環と持続可能な自然と付き合うための、基本の作法とでも言えばよいのだろうか。そうしたことをごく普通のことのようにして布を作られている姿を拝見し、そこから学び得たことは多かった。それは、そのまま現在のIKTTの「伝統の森」という、布と布を作る人々にとって大切な、自然環境を再構築する事業の基本の作法にもなっている。
同じとき、沖縄の織り手で羽衣のような布を織られている方が、そんな羽衣のような布を織るために大切なものは細くてしなやかな生糸だと話されていた。沖縄には志村明さんという、生糸の研究に力を注がれていた方がおられた。しかし、その志村さんが作られるすばらしい糸があるときは、みんながあまり素材のことを気にしていなかった。が、志村さんが沖縄を離れて、そんなすばらしい糸が手に入らなくなり、はじめて志村さんの仕事の意味とその重要さに、みんなの思いが至ったのではないだろうか。石垣島で養蚕が行われているのに、石垣の織り手はその生糸が欲しいと思っても、沖縄には製糸工場がないため、石垣の繭は宮崎の製糸工場に送られ、京都の生糸問屋さんから買わなくてはならない。
志村さんは、座繰りの生糸が持っている風合いの素晴らしさを、改めて問われている。
最近、日本の若い織り手の方たちの中で、自分で綿花を栽培して糸を紡ぐ、蚕を飼い始めたという風のたよりを耳にすることが多くなった。それは、素材をもう一度見直すところからものづくりを考える、そんな時期に来ていることを語っている。本来、いい土があるところで焼き物が起こり、いい水のあるところで染色が行われてきた。その基本に帰ること。
あらためて、伝統は守るものではない、私たち自身の手で作り出していくものが伝統なのである。そのために、素材から見直す。あえて言えば、それを生み出してきた自然環境、風土についてもう一度見直す時期が来ているのではないだろうか。
IKTTは15年前、戦争の中で失われた伝統を再生するために、カンボジアで自然の再生に取り組み始めた。効率化のなかで失われた伝統と自然と結びついた伝統の再構築が、いまの日本でも必要な時代がやってきているのではないだろうか。それはそのまま、自然の再構築の必要性を意味する。
日本でも、15年前にわたしがカンボジアで手の記憶をもったオバアたちを探したように、伝統の知恵をもつ人びとと出会う作業が必要なのかもしれない。久しぶりに今井さんと出会えたことで、そんなことを思いめぐらしながら日本を後にした。
【以上、メールマガジン「メコンにまかせ」掲載記事から抜粋、一部加筆修正】
※記事中にある、96年に開催された『アジアのテキスタイル交流プログラム』については、今井俊博氏によるレポートが、国際交流基金の刊行物「アジアセンターニュース(No.2)」に掲載されています。(「アジアセンターニュース」のバックナンバーは、国際交流基金のサイトにPDFデータがありますので、そちらをご覧ください)。また、石垣昭子さんの紅露工房については、Webマガジン「ナチュラルクエスト」での紹介記事もありますので、そちらもご覧ください。
※挿画は、喜多川歌麿「女織蚕手業草 九(繰糸)」です。
※メールマガジン「メコンにまかせ」の講読は、こちらからお申し込みください(講読無料)。